.png)
.png)
フロン排出抑制法が施行され、業務用冷凍空調機器からのフロン類排出抑制が喫緊の課題となっています。特に、地球温暖化への影響が大きいHFC(代替フロン)の排出量が増加傾向にあることから、フロン類の回収・破壊だけでなく、製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が求められています。
この記事では、環境行政に精通した行政書士の視点から、「第一種フロン類充塡回収業者」の登録について、その要件から具体的な手順、登録後の義務、そして違反した場合の罰則まで、皆様が知りたい情報を網羅的に解説します。これから第一種フロン類充塡回収業を始めたいとお考えの方、既に行っているが改めて制度を確認したい方は、ぜひご一読ください!
1. 「第一種フロン類充塡回収業者」とは?その重要性
1-1. 定義と役割
第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを「業として」行おうとする者を指します。
ここでいう「業として行う」とは、充塡や回収行為を反復・継続して行うことを意味し、営利目的であるか否かは問われません。さらに、自社が所有する機器に対して充塡・回収を行う場合であっても、登録が必要となります。これは、フロン類の不適切な充塡による漏えい防止、整備不良の機器への繰り返し充塡による漏えい防止、異種冷媒の混入防止、そして適切な回収を促進し、オゾン層保護と地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
フロン排出抑制法において、フロン回収・破壊法から変更された点として、従来の回収に加え、充塡行為も業規制の対象とされたことが挙げられます。これは、専門知識がない者による不適切な充塡が、フロン類の大気中への排出、過充塡による機器の不具合・破損、整備不良機器への充塡による漏えいといった問題を引き起こす可能性があるためです。
1-2. 第一種特定製品の範囲
フロン排出抑制法でいう「第一種特定製品」とは、主に以下の要件を全て満たす機器を指します:
• フロン類を冷媒とするエアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器(冷凍冷蔵機能を有する自動販売機を含む)であること。
アンモニア(NH3)、二酸化炭素(CO2)、水、空気、HFO(ハイドロフルオロオレフィン)など、フロン類以外を冷媒とする機器(ノンフロン機器)は該当しません。
• 業務用として製造・販売された機器であること.
• 「第二種特定製品」(自動車リサイクル法の対象となる自動車のエアコンなど)ではないこと.
具体的な機器の種類としては、以下のようなものが挙げられます:
• エアコンディショナー:
◦ 自動車用エアコンディショナー(自動車リサイクル法の対象外のもの).
◦ 鉄道車両用・航空機用エアコンディショナー.
◦ ユニット形エアコンディショナー、除湿機、圧縮式空気調和用リキッドチリングユニット、その他の空気調和機.
◦ 空気調和装置(クリーンルーム等).
◦ 店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機、チラー、スポットクーラーなど.
• 冷蔵機器及び冷凍機器:
◦ コンデンシングユニット、冷凍冷蔵庫、冷蔵庫、冷凍庫.
◦ ショーケース(内蔵型・別置型).
◦ 飲料用冷水器、氷菓子装置、製氷機.
◦ 輸送用冷凍・冷蔵ユニット(冷凍・冷蔵車の荷室部分).
◦ 定置式冷凍・冷蔵ユニット、冷凍冷蔵リキッドチリングユニット.
◦ ユニットクーラー、ヒートポンプ式給湯器、冷凍冷蔵装置(倉庫用・凍結用・原乳用等).
◦ 自動販売機(飲料用・食品用).
◦ 業務用冷蔵庫、すしネタケース、活魚水槽、アイスクリーマー、ビールサーバーなど.
2. 登録の要件 - これがなければ始まらない!
第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、事業を行う区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。例えば、大阪府の業者が兵庫県でも回収を行う場合は、大阪府と兵庫県の両方の知事の登録が必要です。
登録を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
2-1. フロン類回収設備の所有権等
フロン類回収設備を所有していることを示す書類の提出が必要です。
• 自ら所有している場合: 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書などの写し。請求書は不可。
• 自ら所有権を有していない場合: 借用契約書、共同使用規定書、管理要領書などの写し。
• 上記の書類が提出できない場合: 申立書とフロン回収機の実機写真(全体写真とメーカー・型式が分かるもの両方)が必要となります。
2-2. フロン類回収設備の種類及び能力を説明する書類
取り扱うフロン類の種類(CFC用、HCFC用、HFC用、または兼用)と、回収設備の能力(200g/min未満か200g/min以上か)を説明する書類(取扱説明書、仕様書、カタログなどの写し)が必要です。 なお、フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定製品からフロン類を回収しようとする場合は、フロン類回収設備の能力が200g/min以上(合算可)でなければなりません。
2-3. 「十分な知見を有する者」の配置
フロン類の充塡回収にあたっては、フロン類の性状や第一種特定製品の冷媒回路の構造に関する知識、充塡方法、回収作業に精通した「十分な知見を有する者」が自ら充塡・回収を行うか、または立ち会う必要があります。
具体的な資格としては、以下のいずれかを有することが求められます:
• 冷媒フロン類取扱技術者:
◦ 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会認定の第一種冷媒フロン類取扱技術者.
◦ 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構認定の第二種冷媒フロン類取扱技術者 (ただし、取り扱える機器の対象に限定があるため注意が必要。エアコンディショナーは圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力25kW以下、冷凍冷蔵機器は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力15kW以下の機器に限る).
• 冷媒回収推進・技術センター(RRC)認定の冷媒回収技術者.
• 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会).
◦ ※上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者.
• 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会).
• 冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会).
• 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会).
• 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)).
• 自動車電気装置整備士(対象は自動車に搭載された第一種特定製品に限る。ただし、平成20年3月以降に資格取得した者、または平成20年3月以前に資格取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る)
•以下のものでない者.
•心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの.
• 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者.
• フロン排出抑制法や自動車リサイクル法などの法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者.
• 登録を取り消されてから2年を経過しない者.
• 業務の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者.
• 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合..png)
3. 登録申請の手順と必要書類
登録申請は、各都道府県のウェブサイトを通じて電子申請システムを利用するのが一般的ですが、一部の書類は郵送または窓口への持参が必要となる場合があります。郵送のみによる申請は受け付けられていませんのでご注意ください。
3-1. 一般的な必要書類
1. 申請書:
所定の様式に事業所の名称、所在地、回収対象製品の種類、フロン類の種類などを記載します。複数の事業所でフロン類充塡回収業を行う場合は、事業所ごとに申請書を別葉で作成する必要があります。
2. 添付書類
•本人を確認できる書類。
◦ 法人の場合:発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本。
◦ 個人の場合:発行日から3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写し。住民票の提出が難しい場合は、「本人確認情報の利用承諾書」の提出も可能ですが、本人確認に時間を要する場合があります。
• フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類:
◦ 自ら回収設備を所有している場合:購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のいずれかの写し。請求書は不可とされています。これらの書類がない場合は、回収設備を所有している旨の申立書と、回収機の実機の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方。カタログ写真は不可)が必要となります。
◦ 自ら所有権を有していない場合:借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のいずれかの写し。
• フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類:
◦ 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し。これらの書類には、CFC用、HCFC用、HFC用など、回収設備のフロン類の種類と、200g/min未満か200g/min以上かといった回収能力が明記されている必要があります。
3. 誓約書: 申請者等が欠格要件に該当しないことを誓約する書面。
4. 調査票(十分な知見を有する者の資格等取得状況に関する書面):
資格証の写しは不要な場合もあります。
5. 委任状(任意様式):
行政書士等の代理人が申請書を提出する場合のみ必要です。
3-2. 登録申請手数料と納付方法
• 手数料: 都道府県によって異なります。
◦ 例: 大阪府は6,000円(新規)。
◦ 例: 群馬県は5,000円(新規・更新).
• 納付方法:
◦ インターネット申請の場合は、クレジットカードによる納付が一般的です。
◦ 窓口申請の場合は、手数料納付窓口で現金やキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済など)が利用できる場合があります.
◦ 群馬県では、群馬県証紙による納付も可能です.
3-3. 登録の有効期間と更新
• 登録の有効期間は5年間です.
• 有効期間満了後も引き続きフロン類の充塡・回収を行おうとする場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります. 更新申請は通常、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けられます.
--------------------------------------------------------------------------------
4. 登録後の義務と責任 - 継続的な法令遵守が鍵!
第一種フロン類充塡回収業者として登録された後も、フロン排出抑制法に基づき、さまざまな義務と責任を負うことになります。
4-1. 充塡・回収基準の遵守
• 不適切な充塡による漏えい防止、整備不良機器への繰り返し充塡防止、異種冷媒の混入防止などの基準に従って、フロン類の充塡・回収を行う必要があります.
• 漏えい又は故障が確認された場合、原則として、修理を実施するまでは当該製品へのフロン類の充塡をしてはなりません. ただし、環境衛生上必要な場合、被冷却物の衛生管理のため、または事業継続のためといった応急的に充塡が必要な場合に限り、漏えい確認から60日以内に修理が確実に行われることを条件に、1回に限り充塡を委託することが認められています.
• 現に充塡されている冷媒と異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ管理者の承諾を得る必要があります. また、充塡するフロン類は、特定製品に表示された種類に適合しているか、または地球温暖化係数が表示されたフロン類よりも小さく、かつ製造業者等が安全性を認めているものであることを確認する必要があります.
4-2. 証明書の交付義務と情報処理センターの利用
• フロン類の充塡または回収を行った際には、管理者に対して「充塡証明書」または「回収証明書」を交付する義務があります. これらの証明書には、充塡/回収量、フロン類の種類、充塡/回収年月日などの情報が記載されます.
• 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が指定を受けた「情報処理センター」の冷媒管理システム(RaMS)を利用することで、充塡証明書・回収証明書の交付・受理を電子的に行うことが可能です. これにより、管理者はデータの電子的な管理・集計が容易になります.
4-3. フロン類の再生・破壊業者への引渡し義務
回収したフロン類は、自ら再生する場合を除き、第一種フロン類再生業者またはフロン類破壊業者に引き渡す必要があります. これらの業者は、国(環境大臣及び経済産業大臣)の許可を得た者です.
4-4. 充塡・回収量等の報告義務
前年度にフロン類を充塡、回収、再生、または再生業者・破壊業者に引き渡した量などを、毎年度都道府県知事に報告する義務があります. 都道府県知事はその報告内容を主務大臣に通知し、集計結果が環境省ホームページで公開されます.
• 報告対象者(特定漏えい者): 事業者全体で年間のフロン類算定漏えい量が1,000t-CO2以上の者が該当します.
• 算定方法: 漏えいしたフロン類を直接測定することは難しいため、通常は追加充塡したフロン類の総量を漏えい量とみなし、充塡証明書や回収証明書に記載された充塡量・回収量から計算します.
4-5. 点検・整備記録の作成・保存義務
管理する第一種特定製品ごとに、その点検・整備に関して記録を作成し、当該製品を廃棄し、フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存する義務があります. 記録簿には、管理者情報、機器情報、フロン類の種類と初期充塡量、点検・修理の実施年月日・内容・結果、フロン類の充塡・回収年月日・種類・量、修理が困難な理由と予定時期などが含まれます. 記録は紙形式、電子形式のいずれでも可能で、機器を他者に売却する際には、この記録簿またはその写しを相手方に引き渡す必要があります.
4-6. 行程管理制度の遵守(廃棄時)
第一種特定製品を廃棄等する管理者は、原則として、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すか、建物解体業者等にその引渡しを委託しなければなりません. この際、フロン類の引渡し方法に応じて、以下の書面を交付し、それぞれ3年間保存する義務があります:
• 回収依頼書: 直接充塡回収業者に引き渡す場合.
• 委託確認書: 他の者(第一種フロン類引渡受託者)にフロン類の引渡しを委託する場合.
• 再委託承諾書: 第一種フロン類引渡受託者がさらに再委託する場合. また、所定の期間内に引取証明書が交付されない場合や、記載事項に不備・虚偽がある場合は、都道府県知事に報告する義務があります. フロン回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者は引き取ることができません.
4-7. 「みだり放出」の禁止
何人も、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類をみだりに大気中に放出してはなりません. この規定は、フロン排出抑制法における最も基本的な義務の一つです.
4-8. 費用請求の適正化
第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の回収、運搬、再生、破壊にかかる費用を、依頼者である第一種特定製品整備者や廃棄等実施者に対して適正な料金を請求することができます. また、料金の説明を求められた場合は、費用の明細について説明する義務があります.
5. 罰則 - 違反するとどうなる?
フロン排出抑制法の義務に違反した場合、以下のような罰則が科せられます。
• フロン類をみだりに放出した場合: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金. (2021年11月には、東京都でこの違反により、管理者と建物解体業者が全国で初めて検挙・書類送致された事例があります).
• 都道府県知事の命令に違反した場合: 50万円以下の罰金.
• 点検・整備記録の保存義務違反: 30万円以下の罰金.
• 回収依頼書または委託確認書を交付しない、または虚偽の記載をして交付した場合: 30万円以下の罰金.
• 報告徴収に対する虚偽報告や検査拒否: 20万円以下の罰金.
• 算定漏えい量の未報告・虚偽報告: 10万円以下の過料.
• 両罰規定: 法人の代表者や従業員が、その法人等の業務に関して上記の違反行為を行った場合、行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科せられます.
6. まとめと行政書士からのアドバイス
第一種フロン類充塡回収業者の登録は、フロン排出抑制法が求める重要なステップであり、登録後も多岐にわたる義務と責任を継続的に果たしていく必要があります。これは、オゾン層保護と地球温暖化対策という、地球規模の環境問題に直接貢献する社会的責任の重い事業であることを意味します。
法令遵守を徹底し、適正な事業活動を行うことは、罰則を回避するだけでなく、企業の信頼性を高め、持続可能な社会の実現に貢献することにも繋がります。
もし、今回の記事を読んで、申請手続きや登録後の義務についてご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。 環境行政に精通した行政書士が、皆様の事業活動が円滑に進むよう、法的側面からきめ細やかにサポートいたします。
また、最新の情報や詳細な手引きは、環境省の「フロン排出抑制法」ポータルサイトでも公開されていますので、そちらも併せてご確認ください。
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
【初回相談は無料です】
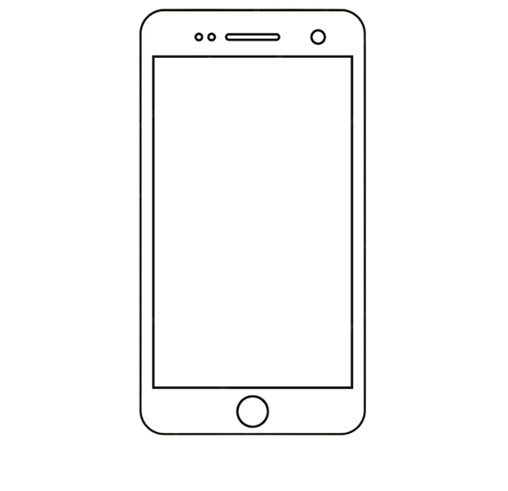 03-6783-6727
03-6783-6727
受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所
.png)

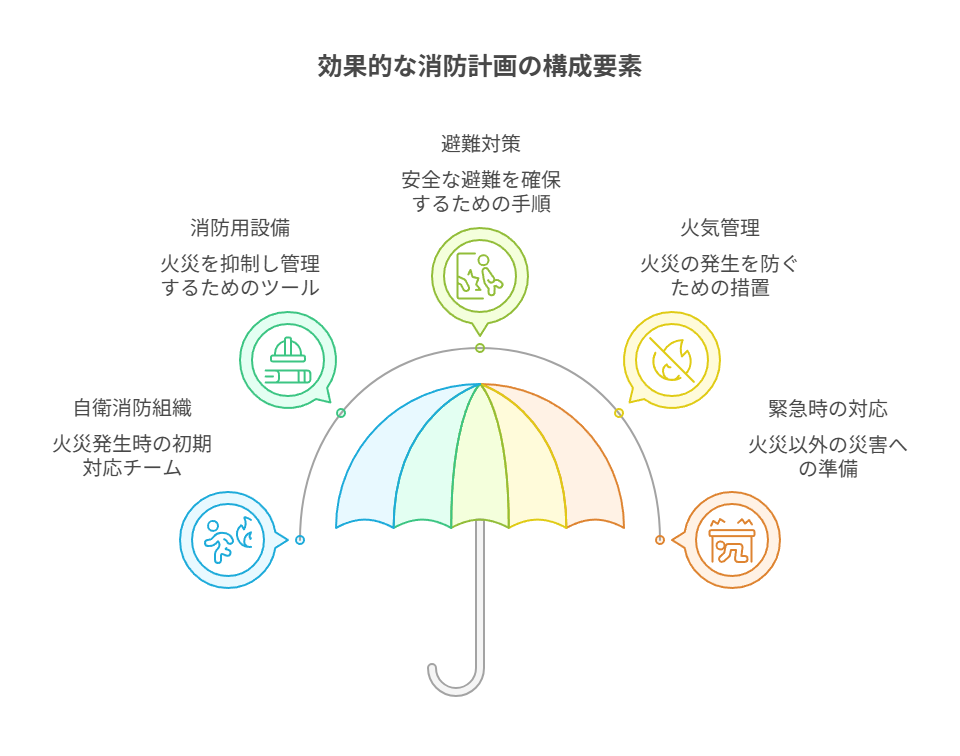
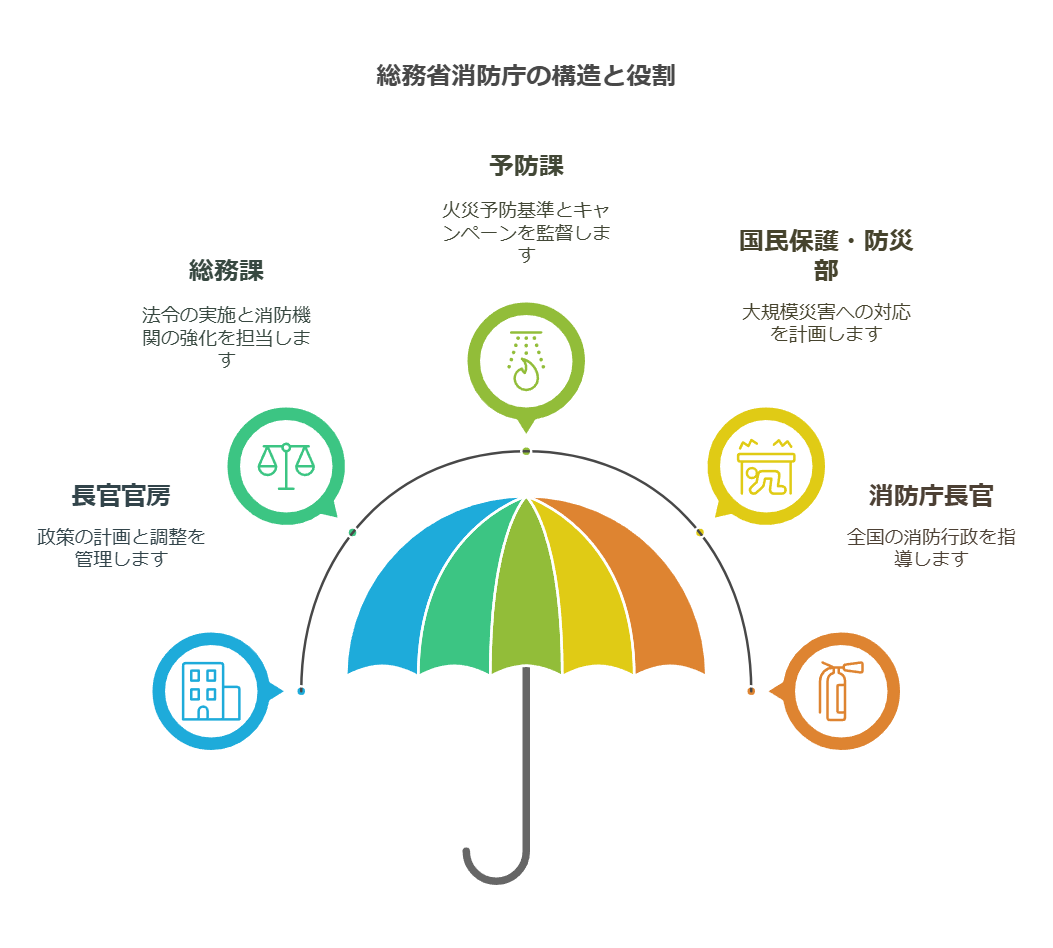

.png)
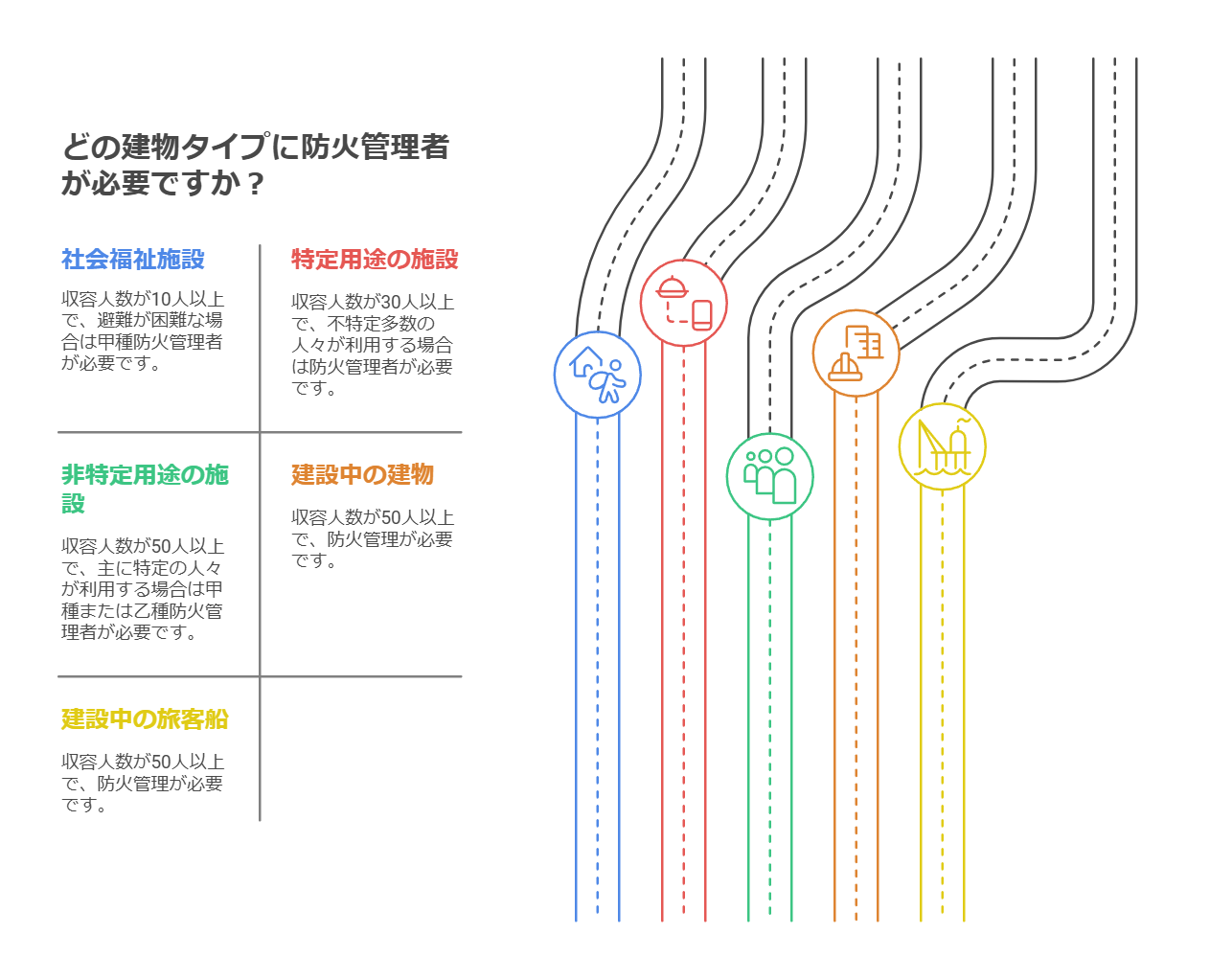
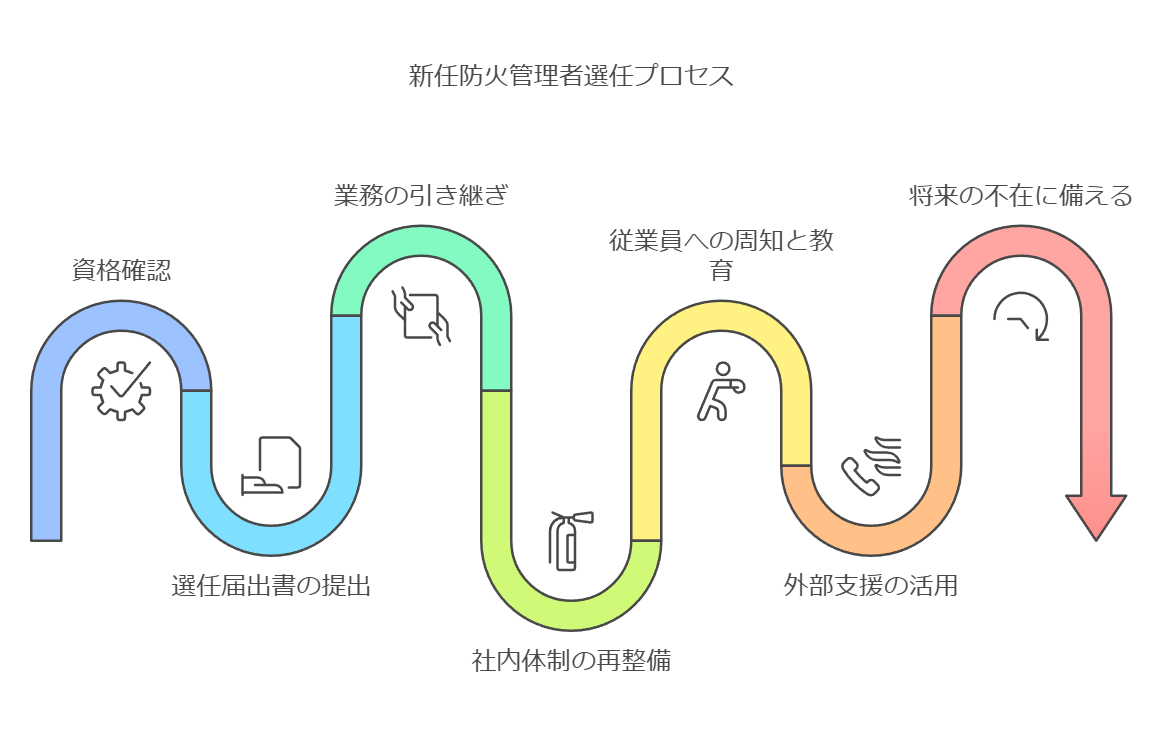
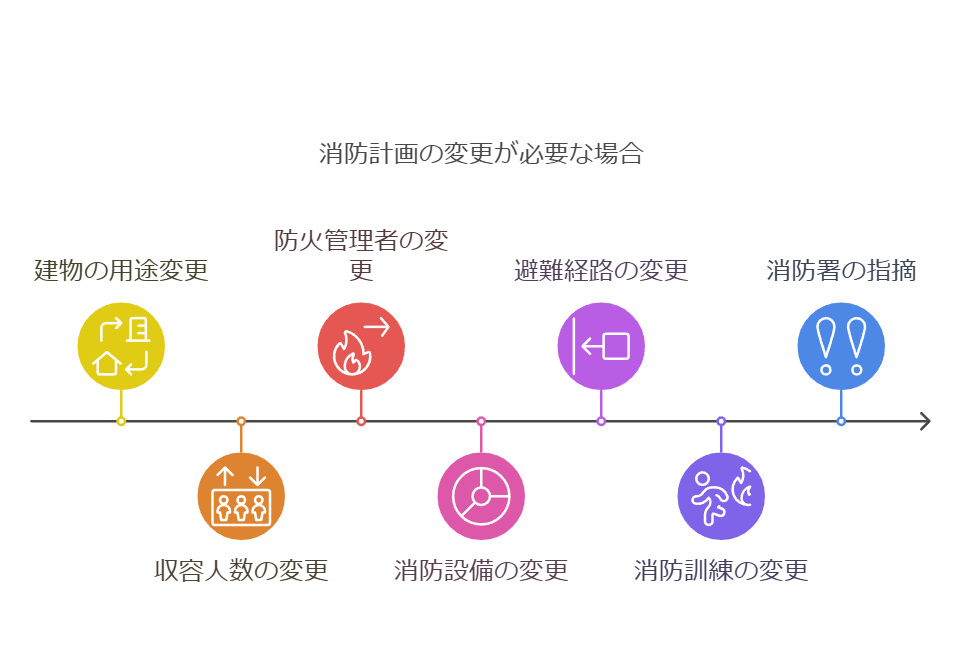
.png)

