1. 原則:用途判定は棟ごとに行う
原則として、同一敷地内に複数の建物(防火対象物)がある場合、それぞれの建物ごとに「政令別表第1」に基づいて用途を判定します。これにより、それぞれの建物に対して必要な防火管理体制や消防設備の設置基準が個別に適用されます。
2. 例外:主用途への「機能的従属」がある場合
ただし、用途の性格上、明らかに「主たる用途」に従属している建物・施設であると認められる場合には、用途判定において主たる用途に含めて扱うことができます。これは、以下のような条件に該当する場合です。
令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて(昭和 50 年4月 15 日消防予第 41 号消防安第 41 号)(最終改正) 平成 27 年 2 月 27 日消防予第 81 号
(1)管理権原が同一であること
建築設備(電気・空調・水道など)の設置・維持・改修等に対して全体的な権限を持っている者が、主用途部分と従属部分で同一である必要があります。
(2)利用者が同一または密接に関係していること
従属部分が主用途部分の職員・利用者の福利厚生や利便性を目的としている場合
外部から独立して出入りできない構造であること(例:道路側からの直接出入り不可)
(3)利用時間が同じであること
主用途部分の利用時間と、従属的用途部分の利用時間が重なることが求められます。
3. 面積基準による「みなし従属」
さらに、以下の2つの要件を満たす場合には、機能的な従属性が明確でなくても「主用途に従属する部分」として扱うことができます。
- 主用途部分の面積が防火対象物全体の延べ面積の90%以上である
- その他の独立した用途部分の合計面積が300㎡未満である
ただし、政令別表第1の(2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(ホテルなど)、(6)項イ(病院・診療所)など、特定の用途に該当する部分は、この面積要件による「みなし従属」の対象外とされています。
4. 用途混在の場合:複合用途防火対象物の考え方
同一の建物内で、政令別表第1の同一「項」内の異なる「号」(イ・ロ・ハなど)が混在する場合には、「複合用途防火対象物」として扱います。この場合、それぞれの用途に応じて必要な防火管理体制・設備を判断しなければなりません。
5. 一般住宅との関係
政令別表第1に定める防火対象物と一般住宅が連続しているような長屋形式の建物については、次のように判断されます。
政令別表の用途部分が50㎡以下、かつ住宅部分より小さい → 一般住宅扱い
政令別表の用途部分が住宅部分より大きい or 50㎡超 → 政令別表対象物または複合用途
両者の床面積がほぼ等しい場合 → 複合用途防火対象物
6. 実務上の留意点
用途判定では、区画(壁・扉など)の有無は考慮されず、利用実態を重視して判断されます。また、機械室やロビーなどの共用部分は、それぞれの用途面積に応じて按分(割り当て)して用途を定めます。
まとめ
防火対象物の用途判定は、防火管理体制の基礎となる重要なステップです。主用途と従属的用途の関係性、面積比率による「みなし従属」、複合用途の判定など、実務上は多様なケースがあります。実態に即した判定を行い、適切な防火管理を行うことで、安全で安心な建築物運用につなげていきましょう。
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
【初回相談は無料です】
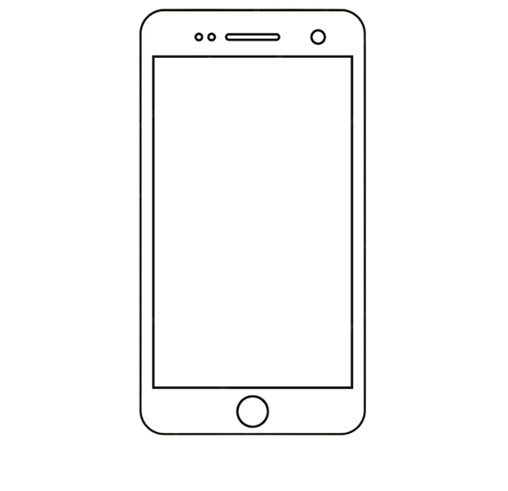 03-6783-6727
03-6783-6727
受付時間 : 08:00~18:00 土日祝日も受付 運営 行政書士萩本昌史事務所
.png)

.png)
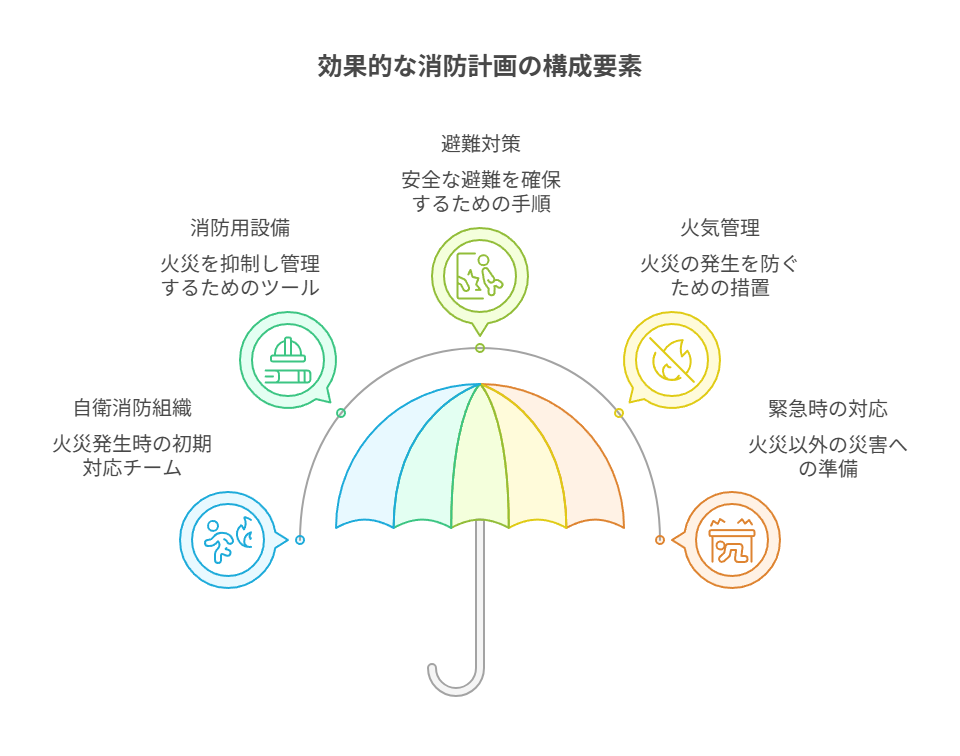
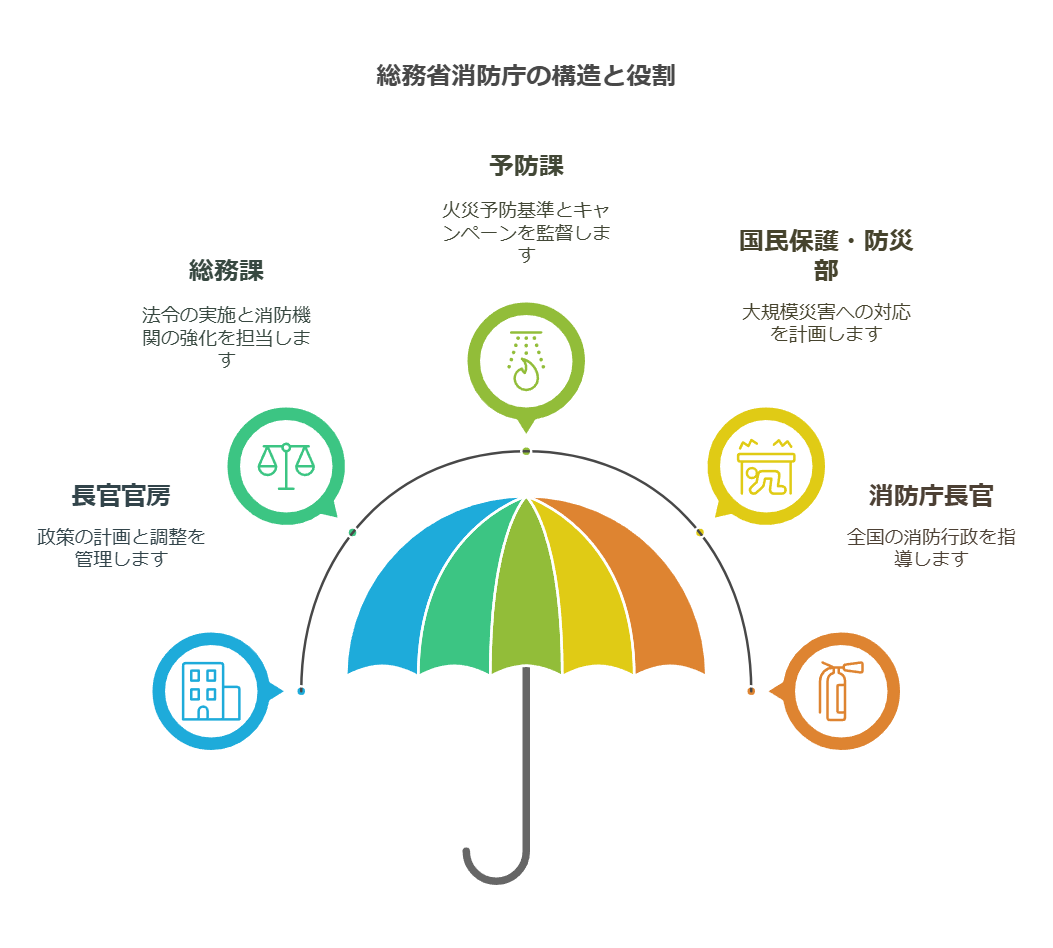

.png)
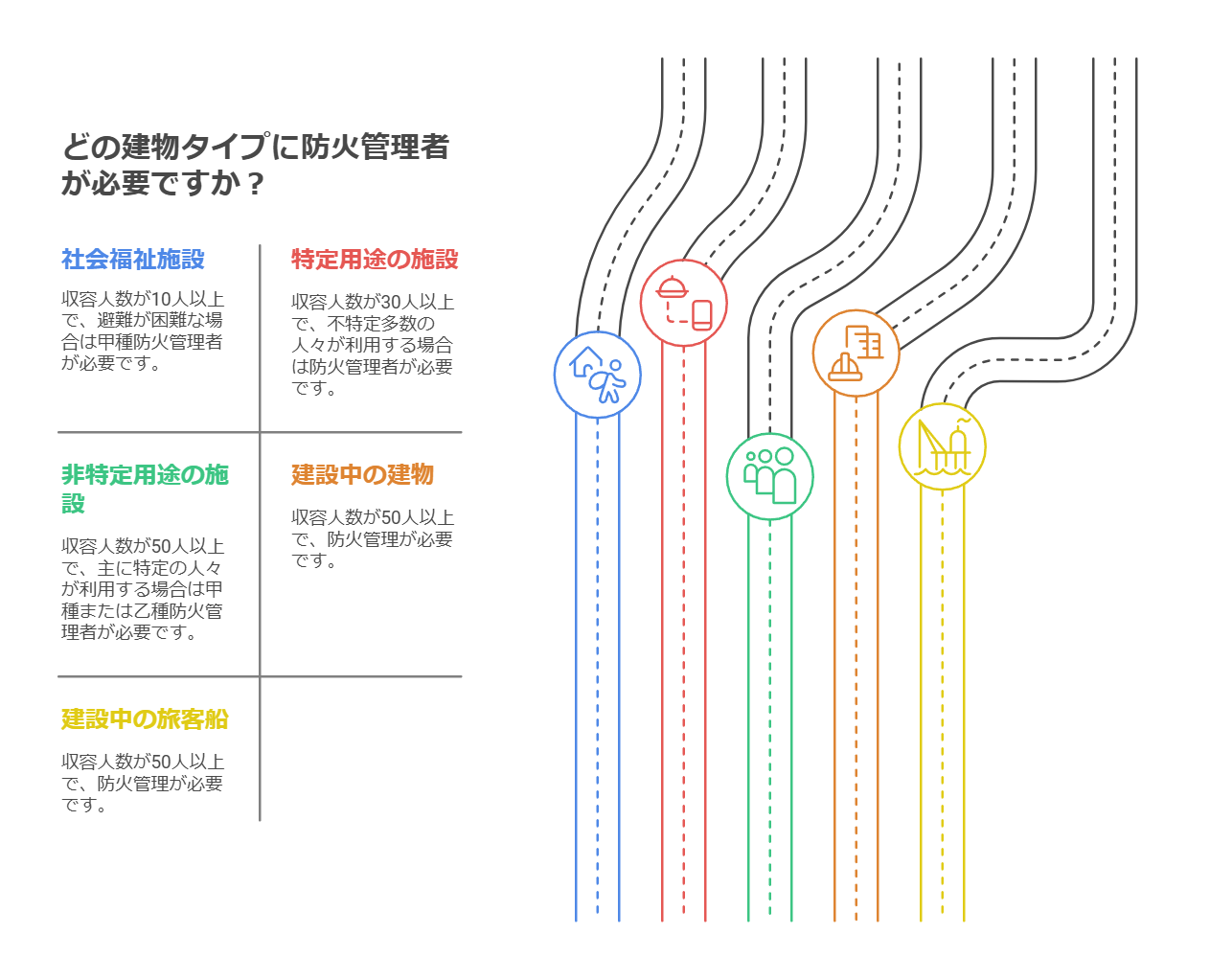
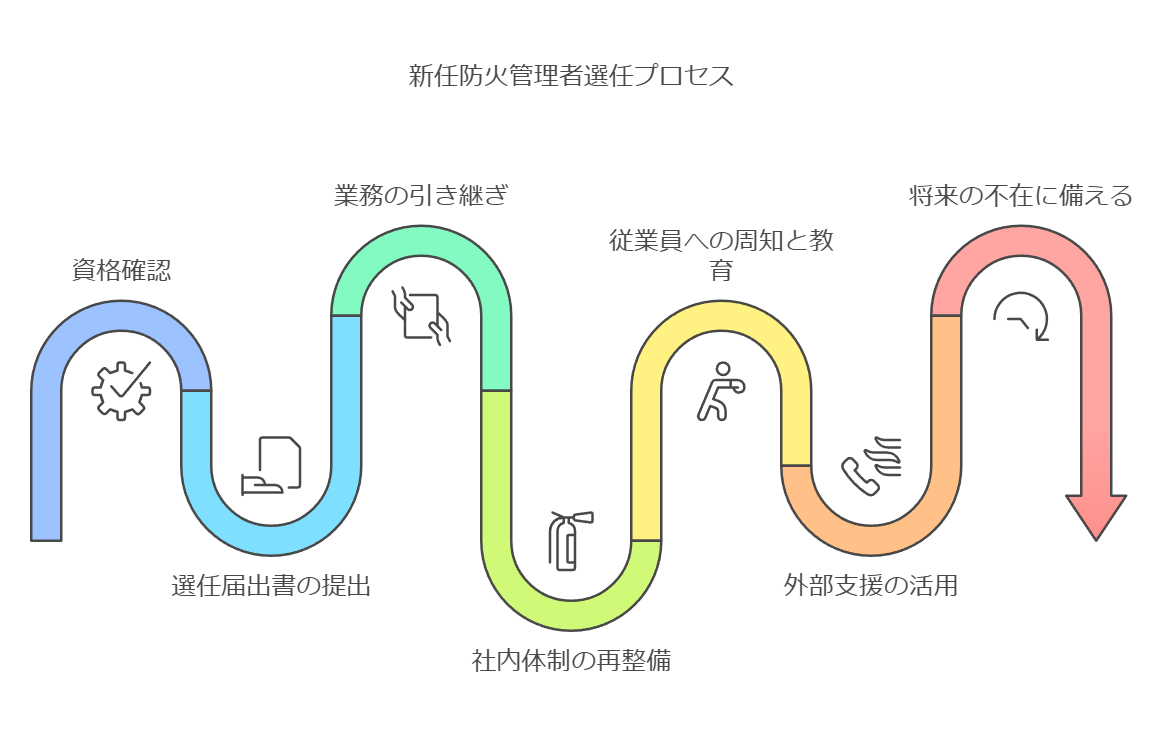
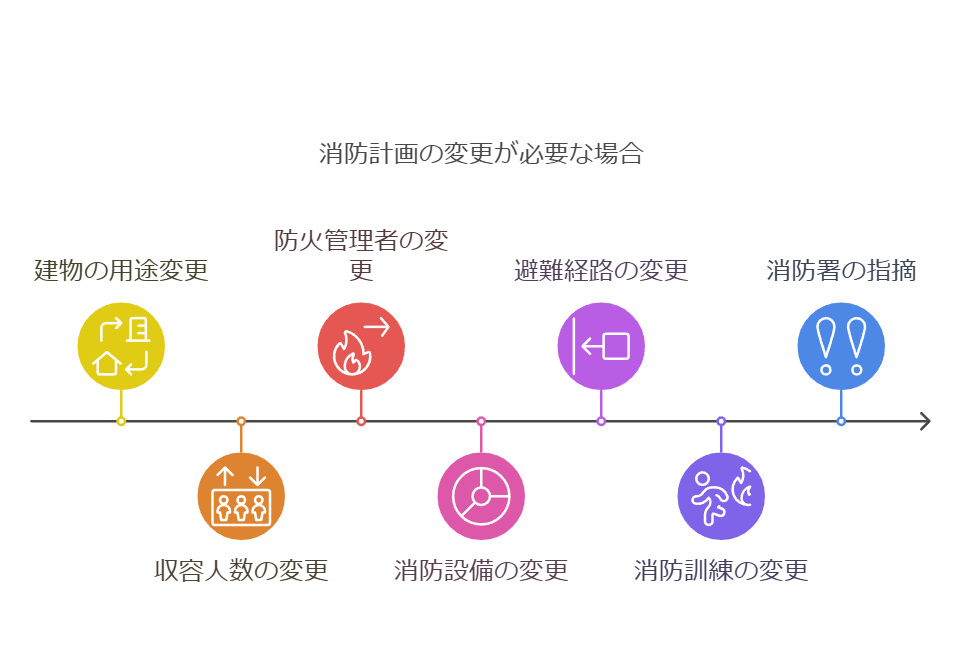
.png)
